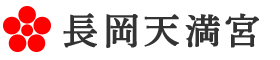神足神社
御祭神 天神立命 (舎人親王と言う説もあり)
鎮座地 長岡京市東神足2-5
御例祭 6月5日
旧神足村の産土の神。式内社で「延喜式」にのる乙訓十九座の一つで「神(こう)足(だにの)神社(じんじゃ)」とみえる。また、文徳天皇の斉衡元年(854)に国の官社にあげられている。当社には「桓武天皇の夢」として次のような伝説が残っている。
< 田村(神足村の旧名)の池に天から神が降り立ち、宮中を南から襲おうとした悪霊を防いでおられた夢を見られたと言う。天皇は目覚められ、田村にこの神を祭る社を建てさせ、太刀と絹を秘蔵させた。>
以後、この社は「神足神社」と田村は「神足村」と呼ばれるようになったと言われる。 また、当社の創建年代は文徳天皇紀齊衡元年に詔ありたるを以て少なくとも八世紀末以前と推定される。

長法稲荷神社
御祭神 宇迦之御魂神
鎮座地 長岡京市長法寺濁り池谷15
初午祭 2月初午
長法稲荷神社がご鎮座された年代は詳らかではありませんが、江戸時代前期に描かれた「洛北屏風」の中に光明寺とともに「明神」(稲荷大明神のことか?)のご神号が画かれており、また天保14年(1843)に作られた「長法寺村絵図」には「稲荷」というご神号が見られますことから、約350年程前にご鎮座になっていたということが推定されます。
御祭神は「倉稲魂神」(うかのみたまのかみ)と申しまして稲の霊の神様、つまり農耕の神様でありましたが、近世になってからはもっぱら商売繁盛の神様として崇敬され、全国4万社という多くのお稲荷様が祀られているのです。そして長法稲荷神社はかっては「西の長法、東の稲荷」と言われたほどご隆盛であったと言い伝えられています。
また、この地域は以前は竹林が繁り昼でも薄暗い処でしたが、現代では都市化に伴い多くの信者に参拝していただくようになりました。そして社も立派になり益々神社としての大きな格式と御力を持たれ、殊に初詣・初午(2月の最初の午の日)には大勢の信者をあつめ盛大に執り行われるようになりました。

走田神社
御祭神 天児屋根命、武甕槌神、経津主神、姫大神
鎮座地 長岡京市奥海印寺走田3
御例祭 10月21日
奥海印寺・長法寺両村の産土神。式内社で「延喜式」にのる乙訓十九座の一つである。祭神は天児屋根命(あめのこやねのみこと)・武甕槌神(たけみかづちの神)・経津主神・姫大神(ひめおおかみ)の春日四柱を祀る。 かっては「妙見社」と言われ寂照院の鎮守であったが、明治以降、正式に「走田神社」と呼ばれるようになった。社名の「走田」は初穂をつくる田を指し、早稲田の守護神であったであろう。尚、1月13日には御千度詣りや弓講が行われる。又明治始め頃まで同じ祭神を祀る小倉神社(大山崎町円明寺)の御輿がこの社まで渉御し、その道がまだ古老たちによって語り継がれている。
暫定登録文化財指定 御本殿、御本殿覆屋

角宮神社
御祭神 左祀 火雷神、玉依姫、建角身命、活目入彦五十狹茅尊
右祀 春日神(三神)
鎮座地 長岡京市井ノ内南内畑35
御例祭 5月1日
境内奥の覆屋のなかには角宮神社本殿(左)と春日神社本殿(右)が並んで建っており、これらはともに嘉永4年(1851)に造営されたものです。本殿の東には八幡宮、大神宮、稲荷社向日神社の小祠四棟が並んでいます。
建立時の拝殿は茅葺の建物でしたが、昭和17年に長岡天満宮から現在の舞殿形式の拝殿が移築されたため、境内の東に移されました。江戸時代につくられたこの建物は、村の鎮守社の素朴な趣を伝えています。
境内入り口の石鳥居は宝永5年(1708)銘のものが建っていましたが、近年不慮の事故で壊れ、平成3年に再建されました。この横に旧鳥居を用いてオブジェが作られ大切に保存されています。又境内に配されている狛犬や石燈篭には、寄進された年や寄進者の名が刻まれ、井の内地区の人々の氏神に対するあつい信仰によって守られてきたようすを偲ぶ事が出来ます。
近年では平成2年に玉垣の整備、5年に旧拝殿(現在神蔵として使用)の茅の葺替えが行なわれました。又平成12年には平成の大修造といわれる、御本殿、各付属建物、境内を囲む土塁等の大掛かりな修復整備が氏子崇敬者のご寄進、官公庁の補助金を受け行なわれました。
暫定登録文化財指定 御本殿、末社(春日社、八幡社)

春日神社
御祭神 天津児屋根尊、姫大神、武甕槌命、斎主命
鎮座地 長岡京市勝竜寺西池田7
御例祭 5月2日
当社は平安時代末期の承安4年(1174年)、九条兼実によって創建されたと伝わる。勝竜寺に隣接して鎮座する。
天正10年(1582年)に焼失し、江戸時代初期の慶長9年(1604年)に再建された。江戸時代後期、破損したために、弘化2年(1845年)に造営された。天正10年の焼失の詳細は不詳だが、近隣の勝竜寺城は、同じ年、本能寺の変を起こした明智光秀が、山崎の戦いで羽柴秀吉に敗れ、逃げ込んだ城である。この混乱や戦乱の影響を当社も受けたのかもしれない。
江戸時代、当社は久貝を除く勝竜寺村の氏神で、現在は氏子の中から宮総代、世話方が選ばれて、お千度や5月2日の例祭が行われている。
境内は門、拝殿と覆屋に入った一間社流造の本殿がある。寛政元年(1789年)の雨屋新建の棟札、弘化2年・嘉永元年(1848年)の普請入用覚(中山弥太郎家文書)と弘化4年(1847年)の簀覆・拝殿の普請願書が残っている。また、石鳥居には元禄13年(1700年)、石灯篭には正徳4年(1714年)、狛犬には慶応元年(1865年)の銘があり、 江戸時代における境内整備がうかがえる。

大歳神社
御祭神 大歳大神、石作大神、豊玉毘売命
鎮座地 京都市西京区大原野灰方町575
御例祭 10月21日
養老2年(718)2月の御創建で、延喜式神名帳山城國122坐中の大社51社の一つに列せられる式内大社である。(神名帳には【大 月次 新嘗】と記される 大社/月次祭に幣帛を受ける神社/新嘗祭に幣帛を受ける神社)大歳大神を主祭神とし、相殿に石作大神、豊玉毘売命をお祀りする。
御神徳は農耕、祈雨、生産、厄除の神様であり、境内は栢の杜(かやのもり)と称し、栢大明神と親しまれてきた。平成7年に京都市の史跡に指定され、栢の実より油を搾り御神灯として使用、紀貫之(古今和歌集の選者)は当社を「かへの杜」と詠った。
大歳の名について本居宣長は『古事記伝』(1798)に「大は稱へ名、トシは田寄の義、田寄を約めるとトシと読む、この神の御霊を以て田を作り、その田より天皇に穀物を寄しまつり給ふ」と記されている。
相殿神「石作大神」は代々石棺などを造っていた豪族の始祖であり、垂仁天皇の皇后、比婆須比売命がお隠れになった時、石棺を献上し、「石作大連公」の性を賜ったと伝わる。合祀年は不詳であるが、社家口伝によると江戸時代後期である。昭和49年愛知県岡崎市石工団地神社に分神する。
現在の御本殿(一間社流造)は元禄3年(1690)の建造物であり、昭和16年に長岡天満宮より移築。同年遷座祭を執り行う。元の本殿は延宝8年(1680)に建てられたものでありましたが、老朽化した為と伝えられている。平成30年に京都府の暫定登録文化財に指定されました。
神楽殿は昭和25年のジェーン台風で倒壊したが、平成25年に氏子の篤志により再建いたした。
毎年10月第3日曜日を氏子祭と定め、江戸時代中期より引き続き金剛流家元による「翁」「栢の杜」の奉納舞がある。この辺りの地域は「翁さんにきてもらわんと稲がみのらん」と伝わっている。
現在、栢の杜を再生するために氏子等と奮闘中。
「影とのみ頼むかひありて露霜に色変わりせぬかへの杜」 紀貫之


大歳神社の兼務神社
・入野神社 京都市西京区大原野上羽町192
・石井神社 京都市西京区大原野石作町586
・八幡宮社 京都市西京区大原野石作町40
・早尾神社 京都市西京区大原野灰谷町丸尾1
・松尾神社 京都市西京区大原野外畑町63
各兼務神社の詳細についてはこちらよりお進みください